営業戦略付きホームページを提供するアズモード
∇Home-Index
−
伸びる会社は知っている
−>第104号一番好きなところを落とす
|
中小企業・個人商店、ITフルパワー活用方法を紹介するFAXマガジンです。
※アズモード社のクライアント向けに、FAXマガジンで配信しているものを再掲載しております。
|
■第104号一番好きなところを落とす
インターネットは道具です。そしてこの道具はその価値と使い方を正しく利用すると今までの常識を覆す結果をもたらします。
2006年9月29日発行号
目次♪
1:新着情報
2:伸びる会社は知っている!→一番好きなところを落とす
閑話休題:心を1gだけ軽くする一言。ダメなときはダメ〜
3:実践テクニック編!〜コンテンツ編(18)〜
4:プロが教えない話外伝!〜私が成功したように〜
5:オススメ情報
それでは始まりです!!!
|
|
1:新着情報
■「Web2.0が殺すもの」9月26日全国書店で発売
ようやくおまけ版の校正が終わりました。
おまけ版プレゼントページと目次見本も完成。
まえがきと、おまけ版の一部を閲覧可能にしました。
よろしければどうぞ。
■Web2.0が殺すもの
http://www.as-mode.com/web20/index.html
ブログで紹介いただいた方はご一報いただければ必ず、ミヤワキ
自身でお邪魔させていただき、コメントさせていただきます。
|
|
2:伸びる会社は知っている!〜一番好きなところを落とす〜
今週から通常通り土曜日発行を予定していましたが、諸事情が重なり金曜日発行です。
そして来週も。
土曜日の発行に決めたのは比較的余裕があることと、週休二日が叫ばれて久しいですが、中小企業の大半は良くても隔週土曜日出社です。
そこで出社した土曜日に「こっちも働いているよ」と届くと嬉しいだろうと考え、また、土曜日が休みでも月曜日の朝一番、休み明けの目覚まし替わりに読んで貰えればというのが理由でした。
発行当初はまさか作家デビューするなんて考えてもいなかったものが、いつの間にやら2作目を刊行し、雑誌にも寄稿するようになり、ありがたいことに本業もばっちり忙しくなり、土曜日発行を守り続けるのが難しくなってしまいました。
すいません。
その2作目ですが残念ながら地元足立区内の書店で「Web2.0が殺すもの」を見かけないのですが、電話で問い合わせたところ北千住の丸善さんでは10冊の入荷分が発売翌日に7冊売れており、残り3冊となっておりました。
草加駅前の高砂書店では即日完売でした。
1冊いれて1冊売れただけですがうれしいものです。
さて、自分の得意分野を決めるのもそうですし、イチオシ商品を選び出すのにも「覚悟」が必要です。
腹を決めるともいいますが、「覚悟」を決めるのに必要な「技術」があります。
それが「捨てる技術」です。
映画作家の大林宣彦監督は編集の際に、どうしても納まりきらない時にはどのカットを落としますかという質問に「一番好きなところ」と答えます。
一番好きなカットには監督個人の思い入れが込められすぎていて、時に全体の流れを阻害していることがあるからだといいます。
映画は配給会社の販売戦略により上映時間が決められます。
その為、泣く泣く「落とす」ことが少なくありません。
ギリギリまで削ってもどうしても納まらないときは、「好きなところ」を落とすというのです。
大林監督と比べるとおこがましいですが、私も前作・今作共に字数の関係からなくなく落とす際にこの言葉を実行しました。
するとびっくり、「すっきり」するのです。
一番好きな箇所はメッセージが濃くなりすぎていて、そこを一段落をまるごと落とすことによって、前後のつながりがスムーズとなり、全体として伝えたいことが分かりやすくなったのです。
落とし(捨てる)てしまうと「覚悟」が決まります。
ホームページやチラシを作る際にはこの「捨てる技術」で覚悟が決まります。
ホームページで、チラシで、何を伝えたいのか? どうでも良いことを捨てていくことによって見えてきます。
しかし映画監督も作家も「モノヅクリ」の人間は作品に対してワガママです。
ワガママの発露がDVD等のディレクターズカットですし、私の著作の「おまけPDF」です。
ボツ原稿なんかじゃありません。
・・・エゴ原稿です。
|
|
3:閑話休題:心を1gだけ軽くする一言。ダメなときはダメ〜〜
なんだか歯車が噛み合わないような時があります。
何をやっても裏目に出て、誤解されたりイヤな奴が集まってきたり。
そんな時は諦めます。
ダメなときはダメなんだと。
但し、投げやりにならないように。
双六でいう「一回休み」何だと思うことにしています。
そして、以前から読みたいと思っていた本や映画を楽しみ、時には仕事もさぼります。
一回休みなんだから仕方ないジャン。
と。
息抜きも仕事のうちです。
|
3:実践テクニック編!〜コンテンツ編(18)〜
小洒落たホームページが量産されるのにはもう一つ理由があります。
経営者がインターネットが苦手という理由です。
Web2.0と馬鹿騒ぎをしたり、ブログに張り付きミクシィ中毒になっている人には信じられないかも知れませんが、メールチェックもしないのにホームページで商売をしている経営者がいまでも佃煮にするほどいます。
私の所には日本全国から相談が寄せられますが、電話での相談が圧倒的です。
メールではどう伝えていいか分からないというのが理由ですが、お客さんからメールで問い合わせがあっても、全部に電話で答えますか? と訊ねると答えに窮します。
つまり自分が苦手なことをお客さんに要求しているのです。
その一方、携帯電話の私信メールチェックだけはしています。
これは「本気」の問題です。
経営者にとって「できない」は「やらない」と同義語なのです。
そして、これではいつまでも自分のホームページの問題に気がつけないのです。
|
4:もっと実践編!〜私が成功したように〜
インターネットの発達によって情報起業家という職種が拡がりました。
御存知のない方のためにざっと説明すると「ノウハウ販売業」で、実は昔からあるものです。
古典は「身長を伸ばす」という漫画誌の裏にあったもので、ペン習字のミコちゃんも広義ではこの範疇にはいるでしょう。
そして最近では「ナンパ指南」や異性とのふれ合いを取り上げた、昔はカッパノベルズやゴマ書房で紹介されていたものが流行しています。
人に相談できないものほど金になるのですが、日本の情報起業家の場合、あらかた市場を食べ尽くすと、起業家プロデュースや、情報起業家開業ノウハウを販売し、これがアムウェイで見たのと同じなのです。
前号で触れたセミナーで、成功者はいいます。
「誰でも成功するチャンスがある!」まともな精神状態なら半信半疑でしょうが、徹夜と集団心理によって傾いている心に畳みかけます。
「私が成功したように」。
詳しくは次号に譲りますが、否定できない正論にはいつも危険が潜んでいます。
|
5:オススメ情報
■ホームページを作る方は必携です。
初心者から初級者にステップアップする際には絶対に必要になります。
http://www.as-mode.com/check.cgi?Code=4798002208
■本の通販ならアマゾンどっとこむ、最速当日届きました(笑)。
http://www.as-mode.com/check.cgi
なぜ?私がアマゾンをオススメするのか?の体験記です。
http://www.as-mode.com/iyashi.html
■ハードディスク丸ごとバックアップ小ネタとファイル整理について
http://www.as-mode.com/recom/hd_backup.html
ミヤワキ及び、アズモード社関連発行のメルマガ
読者数4,100名を超えメルマガ界で注目されるメルマガ
■「マスコミでは言えないこと」
http://www.as-mode.com/mailmagazine/
営業の仕組み作りを実例と共に解説
■「週刊 全員勝利の方程式」
http://www.mag2.com/m/0000140372.htm
あの有名人も行列に並ぶ焼肉店のメルマガ
■「週刊 スタミナ苑攻略法」
http://www.mag2.com/m/0000139932.htm
竹の塚生まれの生粋の足立区民「ケーコ」が送る足立区メルマガ
■「1000%アップ!足立満喫プロジェクト」
http://www.mag2.com/m/0000139929.htm
|
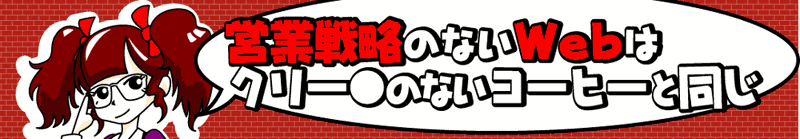
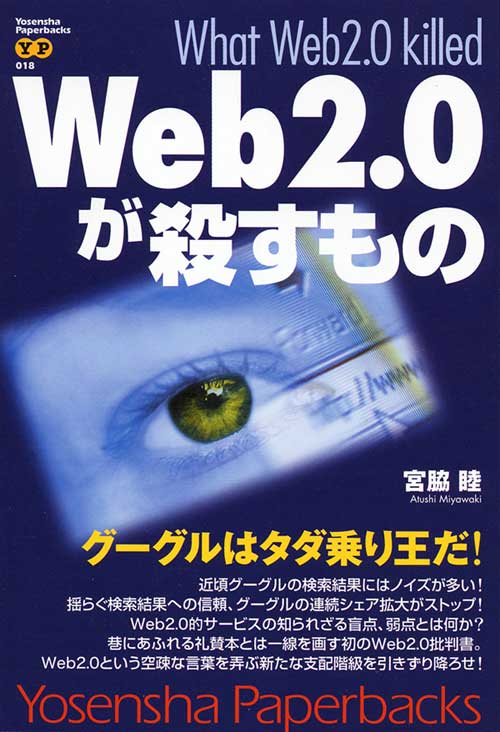 シリーズ第18弾!YosenshaPaperbacks018
シリーズ第18弾!YosenshaPaperbacks018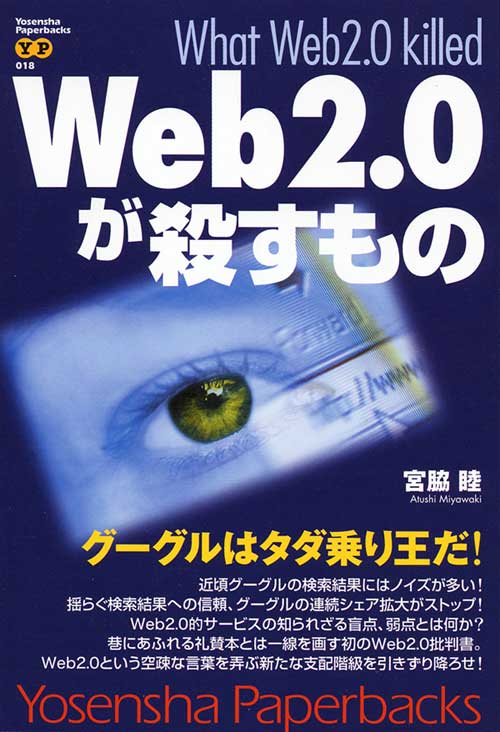 シリーズ第18弾!YosenshaPaperbacks018
シリーズ第18弾!YosenshaPaperbacks018